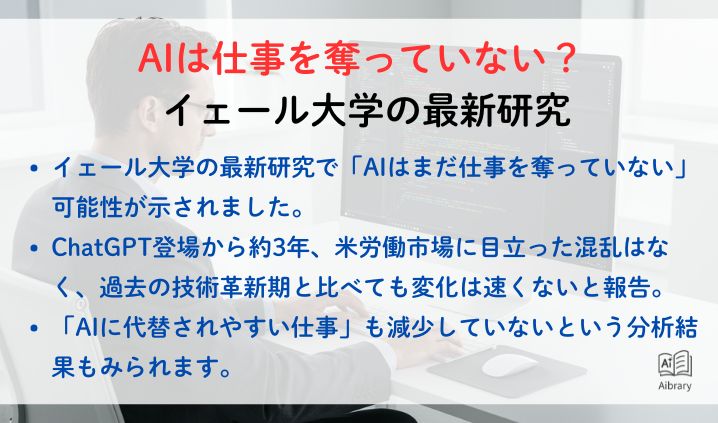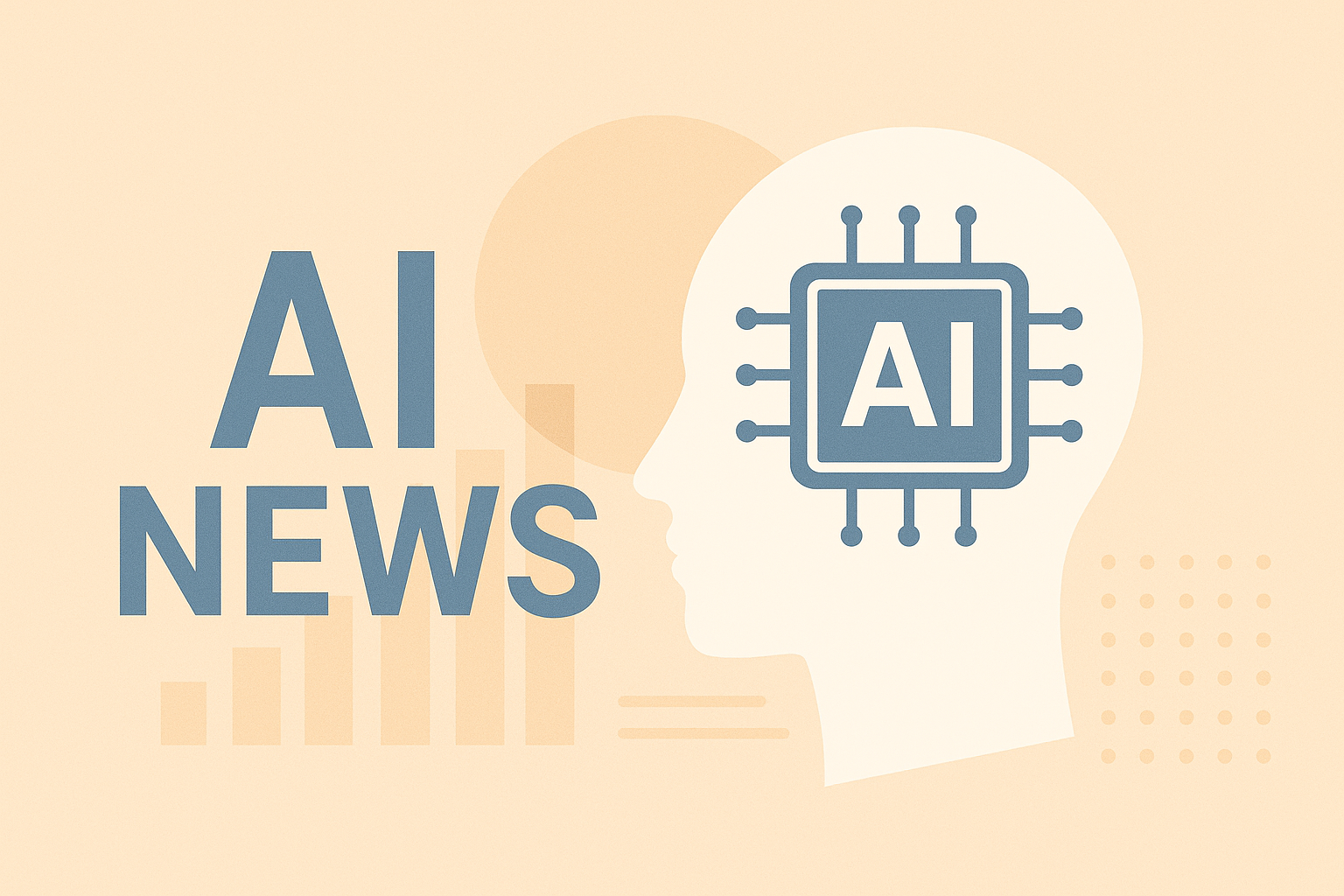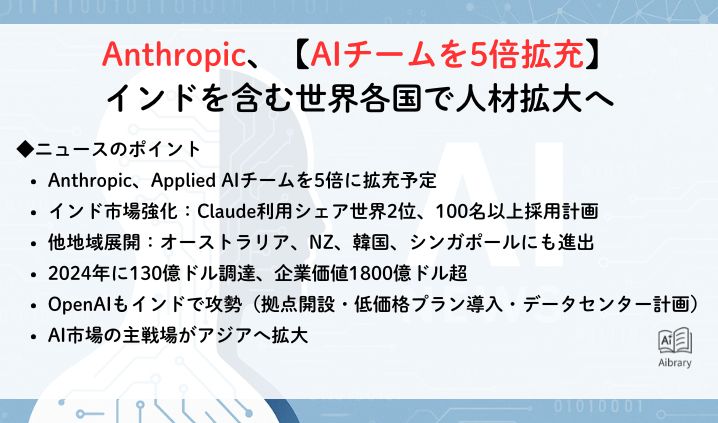防衛省、令和8年度概算要求でAI活用を全面強化

防衛省は令和8年度の概算要求において、AIの導入を防衛力強化の中核施策として位置づけた。無人機群の自律運用からサイバー防衛、後方支援、教育支援まで、多岐にわたる領域でAI活用を推進する計画を明示。
生成AIの導入検討やAI人材育成にも取り組むなど、人口減少や戦闘様相の変化に対応する「次世代型防衛力」の構築を目指す。
【出典・参照元】
防衛省・自衛隊:予算の概要
防衛省・自衛隊:防衛省AI活用推進基本方針と防衛省サイバー人材総合戦略の策定について
AI活用の主な施策(令和8年度概算要求)
| 分野 | 施策内容 | 概算要求額 |
|---|---|---|
| サイバー防衛 | サイバー攻撃対応を支援するAI意思決定システム | 39億円 |
| 基盤整備 | 陸自クラウドにAI基盤を導入 | 25億円 |
| 基盤整備 | 海自通信基盤へのAI導入 | 23億円 |
| 無人アセット | UAV連携型AI駆動UGV研究(輸送・偵察・攻撃支援) | 45億円 |
| 無人アセット | 次期戦闘機と連携するAI無人機の研究 | 49億円 |
| 後方支援 | 補給品需要予測のAI化 | 16億円 |
| 情報収集 | SNS・公開情報の自動収集・真偽分析ツール | 45億円 |
| 事務効率化 | オンプレ環境での生成AI導入検討 | 6億円 |
| 教育 | 学習管理システムにAIを導入し個別最適化教育 | 1億円 |
| 知識資産 | 戦史史料をAIでデータ化・利活用拡大 | 0.8億円 |
| 人材育成 | 外部AI専門家の登用 | 0.4億円 |
| 人材育成 | 隊員向けAI講習(プログラミング等) | 0.1億円 |
| 新技術 | エッジAIで複数誘導弾を制御する「MIRAGE」検証 | 2億円 |
背景
防衛省は、AIを活用する重点分野として「探知・識別」「情報分析」「指揮統制」「後方支援」「無人アセット」「サイバー」「事務処理効率化」の7領域を掲げる。
概算要求にはこれら全てに関連する施策が計上されており、AIが防衛力整備の根幹に据えられることが鮮明となった。
懸念されるポイント・課題
①対抗的サイバー環境での耐性評価の整備状況
自衛隊のAIシステムが敵対的行動(敵によるデータ汚染、モデルの逆操作など)に対抗できるかどうかが重要です。しかし、概算要求の中に「レッドチーミング」や「対抗的評価試験」などへの資金配分があるかは、不明のままです。
②予算規模・継続性の不透明さ
今回の概算要求が「スナップショット的な投資」に留まり、継続的・累積的な予算配分になっているのかは不明です。AI関連プロジェクトでは、長期にわたる試作・評価・運用が鍵であり、年間ごとで終わるような短期視点では効果が限定的になりがちです。
③調達プロセスの硬直性の可能性
概算要求段階では大枠だけが示され、実際の調達プロセスで「小回りの効く試験発注」や「スパイラル的な仕様変更」が可能かは見えません。NATOやRANDが指摘するように、AI装備の実用化には柔軟な調達プロセスが不可欠です。
④運用者との融合設計の不足
AIシステムは現場(部隊・オペレータ)とのインタフェース設計、運用習熟も大きな課題です。概算要求で投入された資源が、どの程度「現場での習熟・教育・訓練」に還元されるかが不透明であり、「現場主導のデータ蓄積」や「運用者に即したUI/UX」の設計が見えづらい点は懸念されます。
⑤倫理・法・説明責任面の担保の程度
責任あるAI適用ガイドラインは策定中ですが、具体的な調達仕様や運用ルールにどこまで落とし込まれて予算化されているかについては確認が必要です。
特に、交戦判断支援や識別支援の分野では、人間関与や説明性を保証するメカニズム(例:ロギング、ブラックボックス解析、承認フローなど)が明記されているかは重要視したい点です。
まとめ
令和8年度概算要求は、AIを単なる補助ツールではなく、防衛力そのものを変革する基盤技術として本格的に活用する姿勢を示した。人員不足や戦闘環境の変化に対応しつつ、自律的で持続可能な防衛力を構築するため、AI活用は今後ますます加速していく見通しだ。