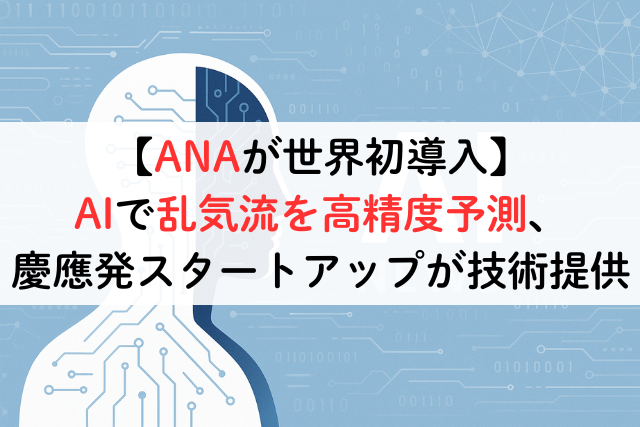生成AI市場、2030年に35兆円規模へ拡大。日本は研究開発で遅れも課題
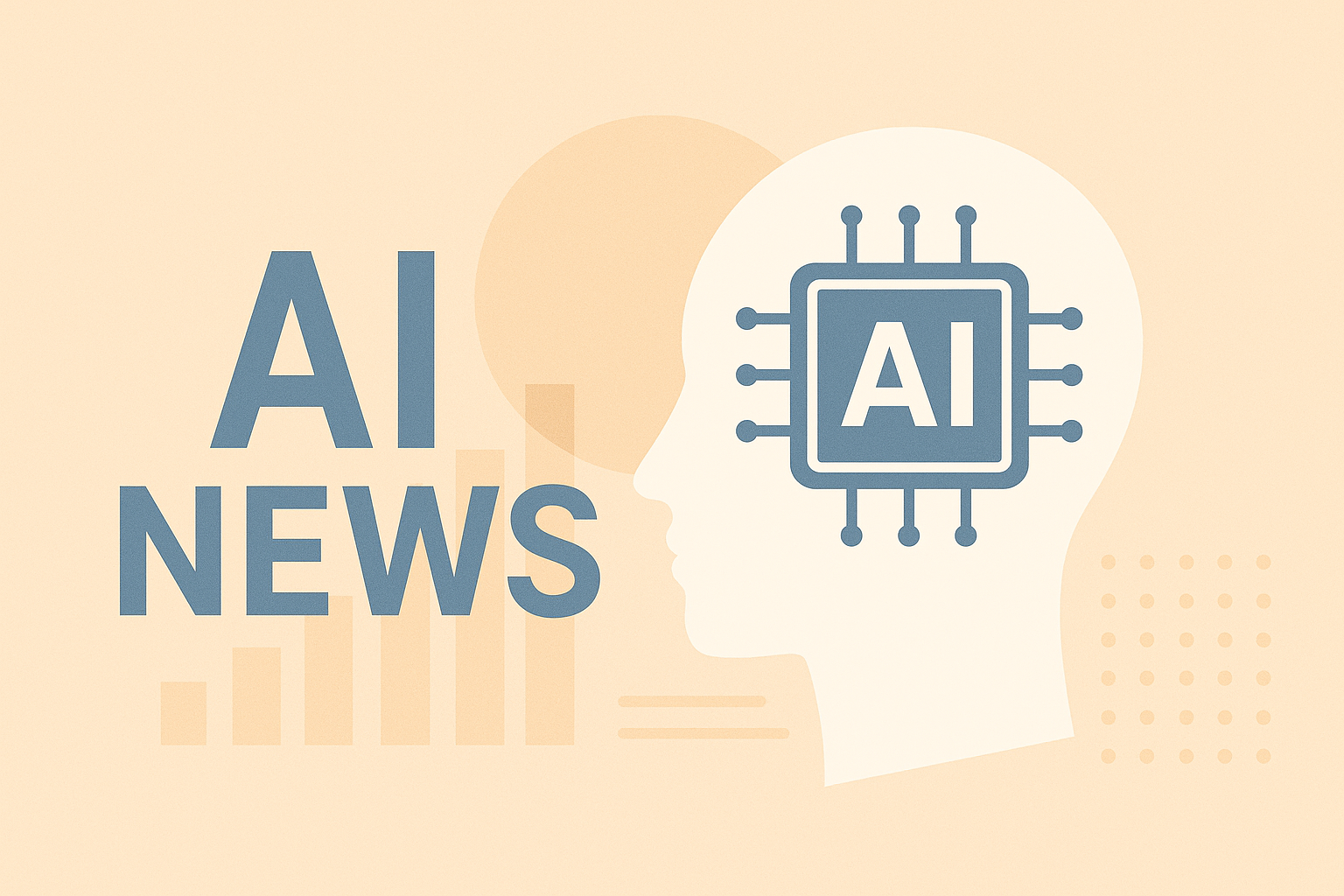
生成AI市場は急成長を続け、2030年には世界で約35兆円規模に達すると予測されている。ChatGPTの登場以降、米国や中国を中心に大規模言語モデル(LLM)競争が加速する中、日本も「Fugaku-LLM」や「PLaMo」などを開発。
しかし国際的な研究ランキングでは9位にとどまり、技術力や人材確保の遅れが課題とされている。今後、日本が競争力を高めるには、独自分野の強化や国際連携が不可欠となる。
◆この記事のポイント
・生成AI市場は急拡大:2030年に約35兆円規模へ、検索・業務効率化・教育など多分野に浸透。
・米中が競争を主導:巨額投資と人材でLLMをリード、日本は研究力や投資規模で遅れを取る。
・日本の独自戦略が鍵:小規模LLMや医療・防災分野での応用、国際ルール形成で存在感を発揮。
【参照】令和7年版 情報通信白書
世界の生成AI市場が急拡大
生成AI市場は、わずか数年の間に驚異的な成長を遂げている。調査によれば、2023年には205億ドル規模だった市場は、2024年には361億ドルへと急拡大し、前年比で実に76%もの伸びを記録した。
さらに2030年には3,561億ドル(約35兆円)に達すると予測されており、今後のデジタル経済を牽引する中核分野になることは確実視されている。
◆世界の生成AI市場規模の推移
| 年 | 市場規模(ドル) | 日本円換算(約) | 前年比成長率 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 205億ドル | 約3兆円 | ― |
| 2024年 | 361億ドル | 約5.4兆円 | +76% |
| 2030年(予測) | 3,561億ドル | 約35兆円 | 10倍以上 |
この急成長の背景には、生成AIが幅広い分野で活用され始めていることがある。従来の検索サービスの置き換えだけでなく、日常業務から専門領域まで多様な用途で導入が進んでいる。
- 検索サービス:従来のキーワード検索から、自然言語による質問応答型の検索へシフト。
- 業務効率化:議事録作成、メール返信、資料要約など、ホワイトカラー業務の効率向上に直結。
- クリエイティブ制作:文章、画像、動画、音楽など、多様なコンテンツ制作を支援。
- 教育・学習:個別最適化された学習プランや、リアルタイムでの質問対応など教育現場でも普及。
こうした用途拡大は企業だけでなく、一般利用者や教育機関、行政分野にまで及んでおり、生成AIが社会基盤の一部として浸透しつつあることを示している。
米中が主導するLLM競争
生成AI市場の急拡大を支えているのが、大規模言語モデル(LLM)の熾烈な競争だ。特に米国と中国の企業が巨額の投資を行い、市場をリードしている。
- 米国勢
- OpenAI「GPTシリーズ」:ChatGPTを中心に世界的な利用拡大を牽引。
- Google「Gemini」:マルチモーダル対応で検索エンジンとの統合を強化。
- Anthropic「Claude」:安全性・透明性を重視したモデルで差別化を図る。
- 中国勢
- DeepSeek:数理推論分野で高い性能を発揮し、注目を集める新興企業。
- Baidu「ERNIE」:中国国内で圧倒的な利用率を誇り、生成AIの商用展開を推進。
米中が優位に立つ理由は、圧倒的な資金力と豊富な人材、そして巨大な市場基盤にある。クラウドや半導体などのインフラ投資を含め、数兆円単位の資金が投じられており、競争は単なる技術開発にとどまらず、国家戦略の一部として進められている。
結果として、生成AI市場の主導権は米中が握っており、欧州や日本はその後を追う立場にある。
日本の取り組みと課題
世界でAI開発競争が激化する中、日本も独自の取り組みを進めている。特に近年は国産大規模言語モデル(LLM)の開発が相次ぎ、国際的なAI市場における存在感を示そうとしている。
- Fugaku-LLM:理化学研究所のスーパーコンピュータ「富岳」を活用した日本発のLLM。
- NTT「tsuzumi」:業務活用を重視した効率的な日本語モデル。
- LINE「HyperCLOVA X」:韓国・日本を中心に展開するアジア圏特化型の大規模モデル。
こうした取り組みは評価されつつも、国際的な「AI活力ランキング」では日本は9位にとどまっている。米中欧と比べて技術力や研究開発力が十分とはいえない状況が浮き彫りになっている。
◆米中と日本の生成AI開発比較
| 国・地域 | 主なモデル・企業 | 特徴 |
|---|---|---|
| 米国 | OpenAI(GPTシリーズ)、Google(Gemini)、Anthropic(Claude) | 巨額投資、商用化とユーザー基盤で先行 |
| 中国 | Baidu(ERNIE)、DeepSeek | 国内市場を背景に急成長、国家戦略と一体 |
| 日本 | Fugaku-LLM、NTT「tsuzumi」、LINE「HyperCLOVA X」 | 計算資源・人材不足で遅れ、独自分野に活路 |
日本が直面する課題
- 計算資源不足:GPUなどAI開発に不可欠な半導体資源の確保が難しい。
- 人材不足:AI研究者やエンジニアの数が欧米や中国に比べ圧倒的に少ない。
- 資金規模の小ささ:研究開発投資が数百億円規模にとどまり、数兆円単位で投資する米中と大きな差。
これらの課題を解消するには、産学官が連携して計算資源や人材を確保し、長期的な投資戦略を描くことが欠かせない。
独自領域での可能性
一方で、日本が強みを発揮できる分野も見えてきている。特に「軽量で効率的なモデル」や「特定領域に特化した応用」だ。
- 小規模LLMの開発:低コスト・低消費電力で動作するモデルは、日本企業や自治体にも導入しやすい。
- 医療・防災・ローカル行政:日本特有の社会課題に即したAI活用に強み。たとえば災害対応や医療格差解消など。
- IOWN構想との連携:NTTが進める次世代通信基盤「IOWN」を活用すれば、消費電力を大幅に抑えたAI基盤の実現も可能。
こうした独自戦略を打ち出すことで、米中の後追いではなく、日本ならではの価値を持つAIを展開できる余地がある。
国際ルール形成での役割
技術開発だけでなく、日本は国際ルール形成でも重要な役割を果たしている。
- 広島AIプロセス:G7を中心に、AIの透明性や信頼性に関する国際的な議論をリード。
- AI事業者ガイドラインの策定:倫理的な利用やリスク管理を明確化。
- 透明性確保と倫理的利用:AIの社会実装を進めるうえで不可欠な基準づくりを推進。
日本は、技術力では遅れが指摘される一方で、「信頼されるAI」や「倫理的AI利用」に関する国際的なルール形成で存在感を発揮している。
まとめ
生成AI市場は世界規模で拡大し、2030年には約35兆円に達する見通しだ。米国と中国が圧倒的な資金力と人材を背景に競争を主導する一方、日本は研究開発や投資規模で後れを取っている現実がある。
しかし、日本には独自の強みも存在する。軽量LLMや医療・防災分野での応用、さらには省電力な次世代通信基盤「IOWN」との組み合わせといった特色ある取り組みは、世界市場において差別化の要素となり得る。
また、AIの透明性や倫理的利用を重視した国際ルール形成において、日本が主導的役割を果たしていることも強みだ。
今後、日本が世界のAI競争で存在感を高めるためには、資源の制約を前提とした戦略的投資と、産学官の一体的な連携が不可欠である。単なる後追いではなく、日本らしい「信頼されるAI」の形を提示できるかが試されている。